岡田暁生『西洋音楽史』中公新書
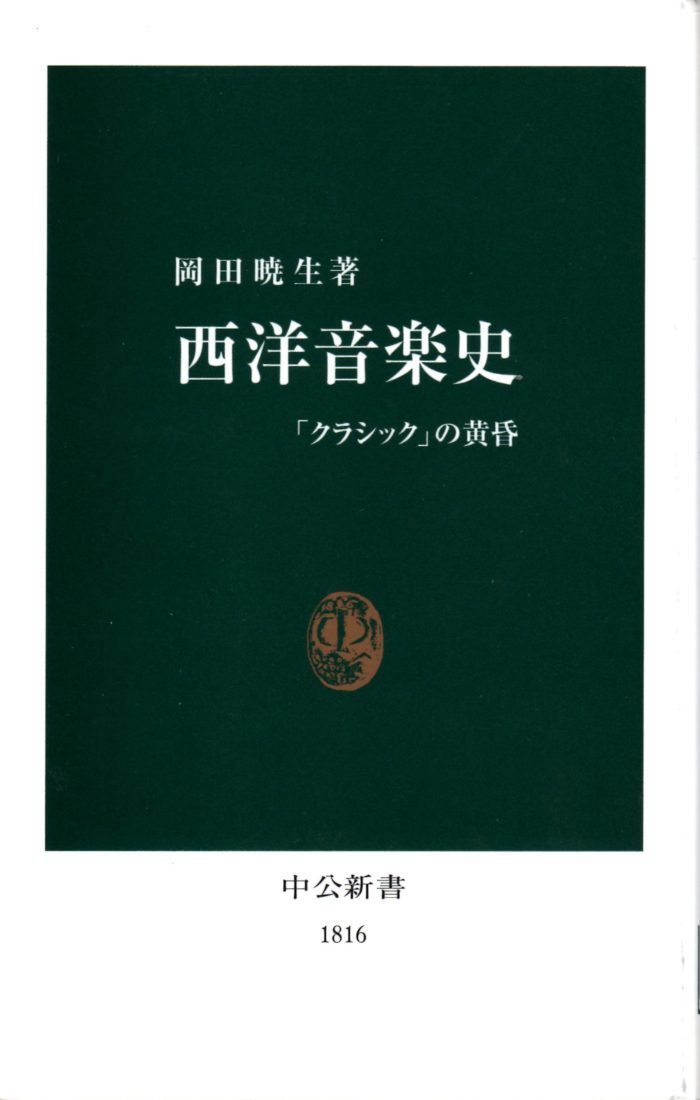
クラシック音楽と総称されている西洋音楽の歴史を、中世、ルネサンス、バロック、古典派、ロマン派、さらには現代音楽までの通史として著したもの。
クラシック音楽にはいくらか馴染んできたと思う。小学生のころは、父の趣味で家には「ステレオセット」と数十枚のLPレコードがあり、私もそれらを時々聴いていた。記憶にあるのは、ベートーヴェンの交響曲5番・6番・9番、ピアノ協奏曲5番、ベルリオーズの幻想交響曲、ドヴォルザークの新世界、ショパンのピアノ協奏曲1番など。いわゆる「名曲」が並んでいた。しかしそれ以上に興味が深まることもなく、クラシック音楽についての知識も、中学や高校の音楽の時間に習うものから大きく出ることはなかった。その後はあまり増えることのなかった父のLP以外にクラシック音楽を聴く機会もなかった。高校生になってFMラジオで音楽を聴く時間はいくらか増えたが、ただ流れてくるものを聞き流しているだけだった。大きく変わったのは大学に入ってからだ。空き時間を大学近くの「名曲喫茶」で過ごすようになり、そこでバッハに魅かれてしまったのだ。特に「平均律クラヴィア」「無伴奏ヴァイオリンソナタ・パルティータ」「無伴奏チェロ組曲」。さらに友人に薦められたモーツァルトやブラームスも聴くようになった。しかしやがてオーケストラはうるさく感じられるようになり、バッハの独奏曲、そして中世のグレゴリオ聖歌へと聞く対象は限られていった。
こんな音楽遍歴の後でこの「西洋音楽史」を読んだのだが、いろいろと示唆に富んでいて、目を開かれることが多かった。特にバッハに関する記述。バッハはバロック音楽の代表ではなく、バロックひいては音楽史の流れから外れていた。バッハを「音楽の父」としたのはドイツナショナリズムで、「軽薄」なフランスやイタリアの音楽に対して「時代を超越した偉大」なドイツ音楽の代表としてのバッハ像がつくられた。こうした音楽史の例外的存在としての、また政治的産物としてのバッハ像を見せられたのは驚きだった。
しかし私にとってのバッハがそれで変わるものではない。ロマン派的情緒に流されるものでなく、ルネサンスのように王侯貴族に媚びることもなく、古典派のように市民階級に受けることもなく、抽象的で数学的な美を示してくれているように思えるからだ。また、抽象性という点では現代芸術に通じるものがあるのかもしれないが、現代芸術が袋小路に入り込んでいるのに対して、バッハは大きく拡がり続けていたのではないだろうか。
音楽を楽しむのに音楽史を知る必要はないし、知ったことで深く楽しめるかどうかも分からない。しかしこの書は、音楽を楽しんできた者にとって、読んで楽しいものだった。


コメントを残す